 住吉周作(九州大学医学部4年生)
住吉周作(九州大学医学部4年生)松木孝之(九州大学医学部2年生)
船田大輔(九州大学医学部1年生)
吉川智子(九州大学医学部1年生)
昨年のホスピス班の活動を通して初めて知った、緩和ケアチームについてさらに勉強し、緩和ケア病棟を持たない病院における緩和ケアチームの役割と重要性、そして現在の問題点を知ることによって、緩和ケアチームの未来を考える。
 住吉周作(九州大学医学部4年生)
住吉周作(九州大学医学部4年生)
松木孝之(九州大学医学部2年生)
船田大輔(九州大学医学部1年生)
吉川智子(九州大学医学部1年生)
2003年8月2日 国立がんセンター中央病院(東京都)
昨年、ホスピス班の活動を行った際に、国立がんセンター東病院(千葉県)の先生のお話の中で、緩和ケアチームの存在を知り、それに大変興味をもったために今年緩和ケアチーム班を立ち上げた。 緩和ケアとは、主に悪性腫瘍及び後天性免疫不全症候群の患者に対して、身体的、精神的、社会的苦痛を和らげることを言い、その形態には、主に以下の3つがある。
今回は、ii.の見学を、下山先生の御指導のもと国立がんセンター中央病院(東京都)でさせていただいた。
下山先生の話によると、緩和ケアチームは
の三者から成り立つということだ。ii.のがん専門の精神科医は珍しいとのことだが、「患者に対して『不安の抑制をする』というレベルで関わらないと、患者は良くならない」と先生はおっしゃっていた。苦痛には、身体的・精神的・社会的・spiritualの四つがある。このような「苦痛を取る」の観点を専門に、がん診断をした時点から、治療ではなく原因を根本的に見つめていくという方針をとってあるそうだ。
「緩和ケアチーム」という用語に関して、厚生省による明確な定義はないが、インターネットで調べた限りでは、「認定基準を満たした病棟をもたない施設などで、緩和ケアに関する専任のスタッフがチームとして緩和ケアを提供する形態」を言い、
から成るということで、大抵の病院で認識されているようだ。病院によっては、薬剤師、栄養士、理学療法士、ソーシャルワーカーなども含めて緩和ケアチームと捉えているところもあった。
緩和ケアチームの活動は、主治医の依頼から始まる。依頼を受けると、チームは病棟へ赴き、患者の診察・家族との面談を行う。その後、主治医や病棟スタッフと連携して緩和ケア実施計画書を作成、患者本人と家族に説明し、同意を得る。あくまで主治医の方針に沿う形で、患者の疼痛の緩和(薬物投与・神経ブロック・放射線治療・理学療法 等)に始まり、ターミナルケアにおける様々な相談を受けたり、在宅ケアのコーディネートも行ったりする。疼痛の緩和に関しては、薬とそれ以外のものを組み合わせて行われ、鍼やお灸の専門医を病院外から招くということも行われているそうだ。どの薬にも副作用は付き物であり、患者に最も合う薬を早く決定し、量を減らしていくのが良いように思える。しかし、逆に薬の見極めを早くしすぎると、選択肢が減ってしまうし、減量することで疼痛の落ち着きが崩れるかもしれない。緩和ケアにおいては疼痛をとることが最優先されるため、薬の副作用とのバランスをとりながらそれを用いているということだ。
日本において、どのような大学が緩和ケアチームを設置しているかというと、
緩和ケア病棟を設置している大学病院は多いが、緩和ケアチームとなるとまだ数は少なめである。下山先生も、「君達が呼びかけて、緩和ケアチームを考える会みたいなものを創ってみては?大学生で緩和ケアチームに注目している団体はまだないから」とおっしゃっていて、後継者を育てたいという思いがひしひしと伝わってきた。
平成14年度の診療報酬改定により、緩和ケアチームを設置した場合、患者さん一人当たり一日につき250点(2500円に相当)分基本診療料が加算されることとなった。これは悪性腫瘍または後天性免疫不全症候群の患者さんのうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体症状または不安、抑うつなどの精神症状をもつ方に対して緩和ケアを行うための十分な体制を評価するために導入されたものである。ただし、この加算をうけるためにはいくつかの条件を満たしている必要がある。
まず緩和ケアチームには以下のスタッフが必要である。
今回私たちが見学させていただいた国立がんセンターではi.は麻酔科専門の先生、ii.は精神科の先生が、iii.は大学院まで卒業された看護師の方がそれぞれ担当されていた。
このチームによる診察と、これに準じた緩和ケア診療実施計画書を作成する必要がある。さらに実施計画について患者さんへ説明をし、同意を得なければならない。さらに症状緩和に関するカンファレンスを定期的に行うことも必要である。国立がんセンターでは週に一回朝8時からカンファレンスが開かれており、私たちはこれを見学することができた。先に述べたスタッフの方に加えて主治医の先生、看護師、薬剤師、ソーシャルワーカーの方なども参加し、患者さん一人一人について今後の方針を議論されていた。そして日本医療機能評価機構などの行う医療機能評価の認定を受けることも必要とされている。
この250点の診療報酬の加算は病院側にとっては魅力的であるといえる。緩和ケアチームが20〜30人の患者さんを担当していれば年間2千数百万の収入となり得るからである。このため条件を満たすスタッフを寄せ集めてとりあえず緩和ケアチームを作るという病院があるのが現実らしい。
患者さん一人当たりの看護職員の人数や入院日数によって異なるが、入院基本料はだいたい800から900点くらいで、それにこの緩和ケア診療料の加算と実際の治療費や食事療養費、場合によっては差額ベッド代を含めたものが緩和ケアチームによるケアを受ける際の月々の患者さんの負担となる。健康保険が適用されるので3割負担となり、また民間の保険会社の保険に加入していれば給付金も支給されるであろう。
このように緩和ケアチームによるケアを受けようとする場合、金銭的には特別大きな負担を強いられることはないであろうと考えられる。ただし一部の有名な私立病院に入院しようとする場合はそれなりの出費が必要かもしれない。国立がんセンターに関していえば、国立であるからベッドが空いていれば入院は可能である。しかし通常は患者さんが多くベッドの空きがないことが多いらしいので、運も必要となってくる。 また国立がんセンターの病室にもランクがいくつかあり、差額のベッド代が数万円から十数万円のものまであるらしい。快適に過ごしたいと考えればそれなりのお金はやはり必要なのだろうか。
今回の見学によりまず医療現場の大変さを改めて認識できた。特に何かをしたわけでもないが、ただ先生についてまわるだけで正直疲れてしまった。医師として働くことは本当に重労働なのだろうなと実感できた一日だった。病室に入れさせていただいて患者さんにお会いできたことも貴重な経験になったと思う。私たち学生に「がんばりなさいよ。」と声をかけてくださった方もいた。あれからもう一ヶ月以上経ったが、お会いした患者さんの中にはもう亡くなってしまった方がやはりいるだろうと思うといたたまれない気持ちになる。期待に応えるためにもこれからもっと自分を磨いていかねばならない。
最後に、このような貴重な経験をさせていただくためにご協力してくださった国立がんセンターのスタッフの方々や患者さんに感謝の意を表したいと思う。
今回8月2日の一日間、国立がんセンター中央病院で緩和ケアとはいかなるものか実際に見学した。以下に一日の流れを示す。
7:50 国立がんセンター中央病院管理棟で今回の研修を快く引き受けてくださった下山直人先生と挨拶を交わす
8:00 国立がんセンター中央病院病棟18階にてカンファレンスに立ち会う
9:10 同じく病棟にて外来の見学
9:40 回診の見学
12:30 昼食
14:00 管理棟にて回診でお会いした患者さんのガン転移の様子をパソコンを使って勉強
15:30 再度病棟にて外来でいらした患者さんの治療の様子を見学
16:20 入院患者さんが神経ブロック療法のためのカテーテルを脊椎に入れる手術を見学
18:30 国立がんセンター管理棟を後にする
今回お世話になったのが国立がんセンター中央病院で疼痛治療・緩和ケア医科長をしてらっしゃる下山直人先生だった。多忙な生活を過ごしていらっしゃる御様子であったが、私たちがする質問に快く答えていただいた。
その下山先生と挨拶を交わした後、早速カンファレンスに参加させていただくことになった。緩和ケアとは、身体の痛みだけを扱うのではなく、患者の持つ全人的な痛みを扱うことである。したがって、緩和ケアのカンファレンスは緩和ケア医だけでなく、精神科医、ガン専門の看護師、ソーシャルワーカー、薬剤師が出席して、患者について話し合いがおこなわれる。話し合いの内容は専門用語が多く、一年生の私には難解なものであったが、わかった範囲でも、検査の日程や、薬についての患者への説明をどのように行うか、患者の主治医の方針と患者の要望の違いを訴えるものなど様々なものがあった。そしてカンファレンスの中では、患者が現在どのような治療を行い、今後どのような治療をしていくか、どのような問題を抱えているかなどを細かに書いた資料を配って、一人一人が患者の様子を知ることができるように工夫しているのが印象的に残った。
ここで、精神科医が緩和ケアにどのように関わるか興味を覚えた。精神科医にかかると聞くと、私は統合失調症や、そううつ病に患者さんがかかっているのだろうかと想像したが、実際には「不安」を診るのだということが分かった。先ほど述べた患者に関する資料の中にも「不安」という言葉があった。「不安」と聞くと漠然として実感が湧きにくく、治療の一環としてまで取り上げる必要があるのか疑問に思ったのだが、患者が自分の病気に対する「不安」が強い場合、不眠につながることもあるときいて納得した。後で回診のときにも気づいたことであるが、緩和ケアの現場では眠れないということが問題になることが多い。痛みか、不安か、何が原因となっているのか突き止める必要がある。したがって患者さんが不安を訴える場合には精神科医がそのケアにあたる。この「不安」を扱うということに関しては精神科医というよりもカウンセラーに近いと言えるのではないだろうか。
次は外来の見学を行うことになった。下山先生が外来で訪れた患者と接する様子を見学した。患者の話を丁寧に聞いた後、下山先生は患者に黄色の大きめな封筒をホッチキスで止めて手渡していたので、後に封筒の中身を質問したところ、中にはカルテが入っていることが分かった。患者は緩和ケア科だけでなく、ガンの治療のために他の科にも行く必要がある。医師と医師との間でカルテを共有し、患者がカルテを無断で見ることの無いようにという配慮から封筒を使っているそうだ。
午前中最後の見学は、入院患者の回診の様子を見学した。下山先生とレジデントの村山先生、ガン専門の看護師の3人で患者さんの病室を訪ね、痛みについての話を聞いて回った。「がん患者」と聞いて何をイメージするか。私はガンによってやつれ果て、日々苦しみながら闘病しているといった浅薄なイメージしかなかったが、実際の現場では、一見してガンにかかっているとわかる人から、ちょっと見ただけでは健康な人とさほど変わらないといった人まで様々であったのが印象的だった。しかしいずれもステージが進行した患者だというのは後で実感することになった。癌の発生部位も卵巣、腎臓、肝臓、すい臓、肺、リンパ、膣、尿管、舌、歯肉、耳下腺、咽頭、食道などそれぞれ異なり、一箇所だけでなく、転移している人も多くいた。患者とは回診の間、いろいろなことを話す。午後10時に眠っても、痛みがひどくて、午前1時に目がさめ薬を飲まなければならないのでどうにかして欲しいと訴える人や、「体が動かないので心配」と声が出せないため筆談で訴える人、経口よりも点滴のほうが楽だという話をする人、転院についてのアドバイスを求める人、幻覚を訴える人、天気によって痛みの度合いが変わることを訴える人、主治医の態度について不満を述べる人などがいた。先生方はそれぞれの患者に対して、じっくりと時間を取って話に耳を傾けていた。そして、患者の話を聞くだけでなく、これからの治療についても話をしていった。意外に思ったのは、国立がんセンターでは緩和ケア治療のために鍼を使った治療も取り入れていることだ。そのために外部から鍼灸師の方を招いているとのこと。このときは意外に感じたものの、後から緩和ケアを行っている病院のホームページを調べてみると、多くの病院が疼痛治療として鍼やお灸を取り入れていることが分かった。
厚生労働省では、在宅医療を全国的に奨めているのだが、社会的バックアップの体制が十分に整っていない現在では、家族の負担が大きく簡単に在宅を進めることができないのが現状である。緩和ケアも在宅で受けることができるようにすることが今後の目標となっているのだが、在宅にしたためにかえって患者や家族の負担が増えるというケースが後を絶たない。回診で出会った、明日から在宅になるという20代の患者の言葉が胸に響いた。「家に帰れるのはうれしいけど、本当に一人でできるのかとても不安です。昨日の夜はそのことを考えて泣いていました。」彼女の不安を正面から受け止める医療が実現していることを願ってやまない。
私たちは回診の際、実に18階から12階まで、階段を使って患者のもとへと移動した。この移動量の多さが私にとって、緩和ケアの本来の姿を実感させてくれることになった。今まで、「緩和ケアとは何か、ホスピスと違うのか、ターミナルケアとは違うのか」、という疑問に対して明確な答えを出せないままに今回の研修を迎えてしまい、疑問は残ったままであった。それでも一応勉強せねばと思いつつ、ホームページで緩和ケアについて調べてみたところ、あるホームページに次のようなグラフがあった。
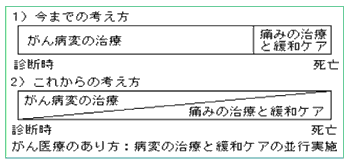 私は今まで、ターミナルケア、ホスピスを考えるとき、どうしても「今までの考え方」を連想していた。すなわち、末期のステージにいる患者は「痛みの治療と緩和ケア」を受けるために専用の隔離病棟に移動するのだろうと考えていた。しかし国立がんセンターでは緩和ケアを受ける患者は、いわゆる「普通」の大部屋にいる人がほとんどであった。緩和ケア専用の病棟はなく、「これからの考え方」にあるような、「治療の一環」として緩和ケアが行われている印象があった。ただ単に国立がんセンターは病棟が限られていて、緩和ケア専用の病棟がない、あるいは緩和ケア病棟が確立していないというわけではない。あらゆるステージの、ガンにかかった患者が痛みを減らす治療に専念できる環境を実現するために、こうした「隔離しない」中での治療を行っているのである。また当然のことながら、末期のステージにいる患者に対して緩和ケアは「看取り」まで行う必要がある。今、私が「緩和ケアとは何か」とたずねられたら、「治療の一環として患者さんが治療に専念できるようにし、患者さんが望む形での、死を実現するもの」というように答えると思う。
私は今まで、ターミナルケア、ホスピスを考えるとき、どうしても「今までの考え方」を連想していた。すなわち、末期のステージにいる患者は「痛みの治療と緩和ケア」を受けるために専用の隔離病棟に移動するのだろうと考えていた。しかし国立がんセンターでは緩和ケアを受ける患者は、いわゆる「普通」の大部屋にいる人がほとんどであった。緩和ケア専用の病棟はなく、「これからの考え方」にあるような、「治療の一環」として緩和ケアが行われている印象があった。ただ単に国立がんセンターは病棟が限られていて、緩和ケア専用の病棟がない、あるいは緩和ケア病棟が確立していないというわけではない。あらゆるステージの、ガンにかかった患者が痛みを減らす治療に専念できる環境を実現するために、こうした「隔離しない」中での治療を行っているのである。また当然のことながら、末期のステージにいる患者に対して緩和ケアは「看取り」まで行う必要がある。今、私が「緩和ケアとは何か」とたずねられたら、「治療の一環として患者さんが治療に専念できるようにし、患者さんが望む形での、死を実現するもの」というように答えると思う。
余談ではあるのだが、下山先生は「バトル・ロワイヤル?」の製作途中で亡くなった、深作欣二監督の看取りをなさったそうだ。その後、バトル・ロワイヤル?の試写会に招待され、内容も知らずに、小学生の娘さんと一緒に行ったところ、あまりの過激さにびっくりしたとのこと。「あのおじいさんが、こんな映画を作っていたとは想像もしなかった」と話しがあった。
昼食には先生方もめったに食べないという、「高級」散らし寿司を囲んで、今までの感想や、部の活動について、先生の個人的な話に盛り上がった。 昼食が終わると、先生の許可をいただいて、午前中回診で会った患者のコンピュータ内に保存されているデータを閲覧することになった。一年生の私にとって、レントゲン、CT,MRIの画像は初め何がなんだかわからないといった状態であったが、先輩方にいろいろと質問していくうちに、なんとなく、画像のどのような部位がガンなのか判別できるようになった。午前中お会いした患者さんの中に、おなかが膨れた患者さんがいて、ただの「中年太りだろうか」、と思っていたのが、実際はがん細胞が腹部全体に広がり、肺を圧迫するまで成長していたことが分かり、ショックを受けた。傍目には体調もよさそうに見えたことに、がんの恐ろしさをより強く実感した。今さらながらに自分がガンについて何も分かっていないことに気がつくことになった。
次は緩和ケアの治療の現場を見学した。当日、神経を「殺す」薬を注射することで、痛みを感じないようにするという治療をするはずだった患者と、下山先生は治療前の説明をしていたのだが、話を聞くうちに、患者の痛みが当初、先生が予想していたものと違っていたようで、その場で治療の変更を患者に勧めることになった。突然の治療の変更に対しても患者に丁寧に話をすることで、患者は納得した様子で治療に同意を示してもらえた。また、先生の患者の話に耳を傾けている姿勢はとても印象的であった。そして治療は手術室の近くの部屋で行われることになった。「注射一本」打つのにも細心の注意を払い、立ち会う人全員が「清潔」にするまではいかないものの、治療に用いる道具は全て「清潔な」物を使っていた。この準備は全て手術室の看護師さんがボランティアでしてくれているとのこと。このような協力があって初めてスムーズに治療を行えるということがわかった。
次は「神経ブロック療法」を行うために、患者さんの脊髄に直接カテーテルを通す治療を見学した。「神経ブロック療法」とは脳脊髄神経や脳脊髄神経節または交感神経節およびそれらの形成する神経叢に向かってブロック針を刺入、直接またはその近傍に局所麻酔薬または神経破壊薬を注入して、神経の伝達機能を一時的または永久的に遮断する方法である。この時は長時間の効果を得るために、硬膜外針を通してカテーテルを留置し、薬液を持続的に注入するという方法をとっていたようだった。見学して思ったことは、たとえ麻酔をしているとはいえ、脊髄に針を刺しいれ、カテーテルを通すのはとても痛そうであること、衆人環視の中痛みをこらえる患者の気持ちはどうなのだろうかということであった。特にこの場合患者さんが自分の意思をうまく表せない患者さんだったので、患者さんの気持ちについて考えさせられることになった。直接脊髄に薬剤を注入する神経ブロック療法は痛みの緩和にとても効果的であることは医学知識のない私にとっても容易に想像できた。
緩和ケア医療はまだ日本ではあまり進んでいない。癌の治療薬に対する専門家(腫瘍内科医)を育てるシステムも最近できたばかりであり、癌専門の看護師、緩和ケア医の数が少ないのが現状である。だからといって、緩和ケア医の必要姓がそれほどないということではない。緩和ケア医というのは、痛みを薬剤によって管理すると同時に、患者の精神的な痛みも引き受ける。薬には副作用がつきもので、効果と副作用のバランスを考えながら、投与していかなければならない。さらに死を目の前にした患者の精神状態を把握し、患者の死と向き合っていくことも必要になる。設備が整っていないのは、緩和ケア医療がまだ新しい分野であるためである。「医師が治療の合間に片手間で・・・」と行うには技術的にも精神的にも大変な負担であることは明らかであり、今後、癌患者が増加すると思われる状況で、緩和ケア医の需要は高まっていくと考えられる。しかし一方で、医療設備が整うにつれ、緩和ケア医療の抱える問題も明らかになっている。緩和ケアチームというのは、麻酔科医、精神科医、専門の看護師によって作られ、緩和ケアチームを病院内で作ることで、一日300点ほどつまり、約3万円が国から支給される。年間にしておよそ2400万円が病院に支給されることになるのだが、そのために、緩和ケアが専門でなくても、病院内で肩書きだけの緩和ケアチームを作り、国からの給付金を“騙し取る”といった詐欺まがいの行為をしている病院も出てきたのだ。このようなことを治療の合間に教えていただいたばかりではなく、他にも下山先生は入院にはどのくらいの費用がかかるのかといった私たちの質問に答えていただいた。患者さんの治療が終わると、今度は他の先生との話し合いがあるからといって解散することになった。下山先生は治験の責任者もしているということで、本当に忙しい様子だった。
さてここからは私事になる。今回の研修をいかに自分の中に生かしていくか、はっきりといって見当もつかないという気持ちである。しかし今回の研修がなければきっと高学年になるまで、緩和ケアに目も向けずにすごしたのではないかと思う。やはり“行動”は“きっかけ”ではないのかという気がした。“行動”はそれ以前の勉強の機会を与え、“行動”後はそれに関して、さらに勉強する機会を与える。まだまだ勉強することも行動することも私には必要であると実感したことをもって報告を終えたいと思う。
厚生労働省の定義によると、緩和ケア病棟(ホスピス)と緩和ケアチームは、以下のように定義される。
主として末期の悪性腫瘍及び後天性免疫不全症候群の患者を入院させ、緩和ケアを行う病棟(一日につき、3780点)
一般病棟に入院する悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群の患者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症状を持つ者に対して症状緩和を行う専従のチーム(一日につき、250点)
ここで、注目したいのが、緩和ケア病棟(ホスピス)が対象としているのが末期のがん患者であるのに対して、緩和ケアチームは末期がん患者に限定せずに、がんの程度は問わず、苦痛がある患者ならすべてを対象としている点である。これならば、緩和ケアチームは、前記の図である「これからの考え方」(4:見学当日の流れについてのグラフ図)に、制度上、そえる内容であると考えられる。
また、緩和ケアの病棟を作れない中小の病院でも、緩和ケアのチームであれば、一般病棟で治療をするわけであるので設立は、緩和ケアに経験のあるチームメンバーをそろえれば不可能なことではないと考えられる。
今回、緩和ケアチームの現場を見て、緩和ケアが治療の一環であるという印象が大変‘自然‘に実感できた。決して末期の患者のみを対象にしているのではなく、身体的、精神的、社会的な苦痛がある患者ならば、すべてを対象とする点が、今まで現場では重要視されてこなかった「がん患者の苦痛の緩和」というテーマの将来への解決策につながるだろう。
全国的に今後、緩和ケアがさらに盛んになり、患者が、末期のみに限らず(がんの程度を問わず)緩和ケアを十分に受けられる環境ができていくことを望む。
*今回、このような全国的にも少ない緩和ケアチームの見学の貴重な機会を与えてくださった、国立がんセンター中央病院緩和ケア医長の下山直人先生に心から御礼を申し上げます。下山先生には、大変良くしていただき、大変感謝致しております。今後、緩和ケアの研究等でお世話になることがあるかもしれません。その時はまた宜しくお願い致します。