 沖縄県具志川市に沖縄中部病院はある。2002年に建て替えられた病院はあらゆる設備の整った大きな病院で、その内部には清潔感と落ち着きが感じられた。中部病院は1次から3次まで対応する沖縄の医療の中心であるが、特に救急医療、戦後からアングロ・アメリカン式の臨床研修制度を導入してきた臨床研修そして、沖縄という地理的特性から離島医療が特色として挙げられる。
沖縄県具志川市に沖縄中部病院はある。2002年に建て替えられた病院はあらゆる設備の整った大きな病院で、その内部には清潔感と落ち着きが感じられた。中部病院は1次から3次まで対応する沖縄の医療の中心であるが、特に救急医療、戦後からアングロ・アメリカン式の臨床研修制度を導入してきた臨床研修そして、沖縄という地理的特性から離島医療が特色として挙げられる。
沖縄に離島における医療を見学するとともに、沖縄本島における離島医療支援体制を学び、離島医療を体験する。
豊福 千賀 班長 (九州大学医学部 3年)
宮原 麗子 (九州大学医学部 3年)
座光寺 正裕 (九州大学医学部 1年)
8月4日〜8月13日 沖縄県立中部病院 西表島西部診療所 鳩間島の巡回診療
離島医療。沖縄を初め鹿児島、長崎、北海道などたくさんの島を抱える都道府県では常に慢性的な医師不足が指摘されている。いかにして医師を確保するか。それは医療技術が高度に進化し専門化が進み、都市に人が集中する現在では、ますます深刻化していく問題ではないかと思う。実際、離島医療という問題を解決、改善するためにどのような取り組みが行われ、そこで働く医師はどのように感じ、島の住民はどのように感じているか、10日間という短い期間ではあったが、沖縄県立中部病院、西表島西部診療所を訪ね医師たちから話を聞いた。幸運なことに西部診療所の岡田医師が、医師のいない鳩間島に巡回診療に行くということで同行させていただくことができた。さまざまなバックグラウンドを持つ医師たちから話を聞くことができ貴重な体験となった。以下、中部病院、西部診療所、鳩間島の巡回診療から私たちが聞いたこと、感じたことを記す。
 沖縄県具志川市に沖縄中部病院はある。2002年に建て替えられた病院はあらゆる設備の整った大きな病院で、その内部には清潔感と落ち着きが感じられた。中部病院は1次から3次まで対応する沖縄の医療の中心であるが、特に救急医療、戦後からアングロ・アメリカン式の臨床研修制度を導入してきた臨床研修そして、沖縄という地理的特性から離島医療が特色として挙げられる。
沖縄県具志川市に沖縄中部病院はある。2002年に建て替えられた病院はあらゆる設備の整った大きな病院で、その内部には清潔感と落ち着きが感じられた。中部病院は1次から3次まで対応する沖縄の医療の中心であるが、特に救急医療、戦後からアングロ・アメリカン式の臨床研修制度を導入してきた臨床研修そして、沖縄という地理的特性から離島医療が特色として挙げられる。
沖縄では戦後ひどい医師不足であった。そのため離島やへき地では医介輔や保健所に頼った医療が行われていた。これは医師を教育する立場の者がいなかったため、若い医師が本土から沖縄に戻って来られなかったことが理由のひとつにある。この医師不足を教育的な面から支え、発展してきたのが中部病院である。米国からきた指導医のもとアングロ・アメリカン式の研修制度をとりいれ、教育病院として沖縄の中心的な役割を果たしてきた。
また、離島医療の支援体制においても全国的評価を得ている。離島医療で一番大きな問題とされるのは、やはり医師の確保である。沖縄には18診療所あり、そのすべてに常に医師を配置することは大変なことである。そこで沖縄では中部病院で研修した若い医師を1年間離島医療に従事させることでその医師不足を解消してきた。現在の臨床研修は2年間ローテートのプライマリケア医コースと1年目にローテートし2年目に専門科のローテートを行う一般専門医コースに分かれて実施されている。初期研修2年間は終始救急当直にあたるなど救急医療研修を重視している。特にプライマリケアコースを終えた医師は離島診療所に派遣されるため、急性疾患に対応できるようになり、離島で単独でも診療できるようになることを目的とした臨床研修が行われている。研修後は1年間離島で働くことになる(自治医科大出身者は2年間)。現在18診療所のうち7,8割は自治医科大卒業者も含めた中部病院出身者である。
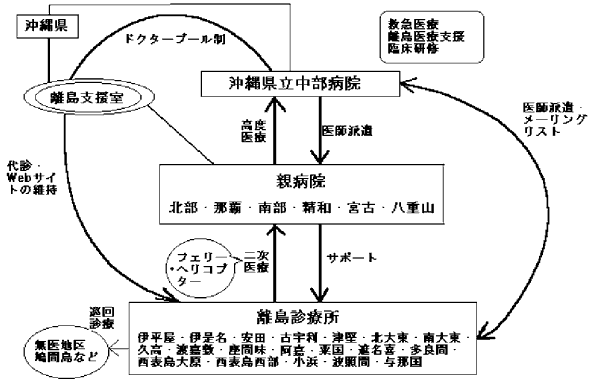
離島診療所には重症の患者に対応するだけの十分な設備はない。そのため重症の患者はフェリーやヘリコプターで親病院と呼ばれている近くの大きな病院へと搬送される。親病院とは石垣島にある八重山病院や、宮古島の宮古病院、本土にある北部病院、南部病院、那覇病院などの県立病院である。中部病院は津堅診療所の親病院としての役割を持つと同時に、親病院ではできない高度な医療を必要とする患者が搬送され、3次医療を行う病院でもある。中部病院にヘリポートはないため、直接離島からヘリコプターで搬送されることはない。つまり、離島診療所の医療を主にサポートしているのは親病院でありその後ろに中部病院が控えていることになる。
今回、中部病院では本村医師と離島支援室の田仲医師の2人にお話を伺った。本村医師は中部病院で研修をした後、伊平屋診療所で1年間勤務し、その後宮古病院を経て中部病院に戻ってきた。田仲医師は現在離島支援室のポジションに就いて離島で働く医師のサポートをしている。田仲医師は離島で計8年間も勤務した医師で、その経験を生かして県行政と離島診療所とを結ぶ役割を果たしている。二人の医師に診療所での経験とその問題点、これからの課題についてお話を伺った。
研修後離島に行き、初めにとまどうことは「慢性疾患の患者を診る機会のほうが多い」ということだそうだ。中部病院で診る患者の大部分は急性疾患の患者で慢性疾患の患者をじっくり診るということはない。離島の患者の大部分は慢性疾患のお年寄りであるため、急性疾患ばかり診てきたそのギャップに戸惑うそうだ。離島に派遣される前に前の医師から引継ぎする期間が1週間でもあれば離島の状況がわかり少しでも精神的な負担がなくなると思われるが、現在はそのようなものはない。また離島では校医の役目も検診、保健福祉の仕事もしなければならない。がそのようなことを教えてもらうことはないので、自分で動いて調べなければならないそうだ。2年間という短い研修期間で離島医療にすべて対応できる医師を養成することは難しいかもしれないが、離島に行く前のサポートをもっとすることが必要であると感じた。
離島に派遣される義務の期間は1年間。それから期間を延ばす人もいるが概して2,3年ぐらいである。1,2年という短い期間で医師が変わることを島の人はどのように思っているのだろうか。まず短い期間で医師が代わる事の利点としては、?一定のレベルの医師が常に離島診療所にいるという状況が作れる。?一人の医師に負担をかけることを防ぐ。?医師が最新の医療から遅れることを防ぐ。ことなどが挙げられる。しかし一方で島の住民の感情からすれば一人の信頼できる医師がずっと診察してくれる方が安心につながるであろう。先生方も島を離れる時引き止められることがあったそうだ。どちらが良いか、意見が分かれるところだと思うが現在沖縄のシステムで医師の確保ができているということを考えれば中部病院のシステムは十分な成果をあげているといえるだろう。島民も離島医療の現状を理解して慣れていると先生方はおっしゃっていた。18診療所常に医師がいる。それを実現することこそが沖縄県の役目なのである。
さて診療所での生活を終えて、中部病院に帰ってきた医師は離島医療のことをどのように考えているのだろうか。残念なことに日常の業務の忙しさに追われて、離島の経験も忘れていき病院的発想になってしまうそうだ。せっかくの離島医療の経験が今後のために十分に生かせていないように感じた。また、中部病院は離島医療の支援の中心であるのに離島経験者以外は離島医療のことを気にとめていることもないようだ。それらの事実はちょっともったいない気がする。なんらかのフィードバックを行い、中部病院の医師がもっと離島医療の現実に敏感になればさらに診療所と医師とのコミュニケーション、連携がうまくいくのではないかと思う。
今回初めて田仲先生のような県の離島医療に関する役職につくドクターの存在を知った。県の行政側から離島支援を行っている医師は2名である。その2人が代診つまり休暇をとる医師や学会などに参加する医師の代わりに診療業務を行っている。その日数は年間100日にもなる。将来的には短期間なら離島に行ってもいいと言う医師を含めてローテーションを組めるようなドクタープール制の導入を考えているとおっしゃっていた。他には若い医師が離島医療に抵抗無く入れるような研修プログラムも考案中とのこと。現在、代診の他に診療についての医学的な疑問、あるいはメンタルな相談も気軽にできるWebサイトの維持・管理や医学情報に触れられる機会を作ることに尽力している。島の医師が孤立感を抱かないための活動をサポートしつつ、県の行政に島の診療所の要望を報告するなど診療所と行政とを結ぶ役割を果たしている田仲医師らの試みはまだ始まったばかりだがその必要性を強く感じ、さらに内容が充実していくことを願うばかりだ。
「けっして赤ひげではない普通の人が普通にできる離島医療」を実現するために活動している、と田仲先生は強調していた。私たちはその言葉が一番印象に残った。赤ひげでない普通の医師が普通にできる離島医療。それは一人の医師にその地域の医療をすべてまかせてしまうのではなく、多くの人が関わって診療所を支える医療である。島の人は赤ひげのような医師をもちろん望むだろうが、24時間365日何年もその地域の医療に従事し自分のすべてをその地域の医療に捧げるような医師を、18診療所すべてに派遣することは不可能なことである。普通の医師が1年や2年離島医療に従事したとして、医師にとっても島の人にとってもマイナスにならないような制度を確立することが大切だと思う。(1章 文責:宮原)
 石垣島から船で西へ向かう。20分ほどすると西表島が見えてくる。途中に見える竹富島や小浜島とは違って、西表島は島という感じではない。まるで大陸がここから始まるかのような印象を受ける。とにかく大きく、高い。そして緑であふれている。
石垣島から船で西へ向かう。20分ほどすると西表島が見えてくる。途中に見える竹富島や小浜島とは違って、西表島は島という感じではない。まるで大陸がここから始まるかのような印象を受ける。とにかく大きく、高い。そして緑であふれている。
西表島は沖縄県では沖縄本島に次ぐ2番目に大きな島で、面積289.27平方?、周囲129.99?である。90%が亜熱帯の原生林で、大部分は未だ人が入ったことのない秘境なのである。一周道路はない。西部と東部を結ぶ道路が島の周囲約3分の2を走っているのみである。原生林で覆われていて、標高400m強の山がいくつもあるため、川が多く、島には珍しく水が豊富である。そのため古くから米が作られ、祖納、星立、古見などは歴史ある区域で、古来の祭りも残っている。自然保護のため、開発はあまりされていない。空港もなく、発電所もない。電気は石垣から海底ケーブルで送られている。
人口は2056人(平成14年9月末日現在)。主に西部地区と東部地区に人が居住している。西表島には東部の大原地区の大原診療所と西部の祖納地区の西部診療所の2つの診療所がある。
 西表島西部にある古い集落の一つの祖納に西表西部診療所はある。西部地区の約130人を対象としていて、このうち300から400人がこどもであり、乳幼児は100人弱である。 診療所には常勤の医師・看護師・事務がそれぞれ1人ずついる。診療所内には、診察室、処置室、レントゲン室、経過観察室、事務室、待合室がある。軽い外科的な処置もできるようになっている。
西表島西部にある古い集落の一つの祖納に西表西部診療所はある。西部地区の約130人を対象としていて、このうち300から400人がこどもであり、乳幼児は100人弱である。 診療所には常勤の医師・看護師・事務がそれぞれ1人ずついる。診療所内には、診察室、処置室、レントゲン室、経過観察室、事務室、待合室がある。軽い外科的な処置もできるようになっている。
患者数は、平日が日に20〜25人、時間外・休日が月に30〜40人である。月曜日と金曜日が多い。1年の中では、観光客の影響で、夏場が特に多くなる。西表西部診療所での主な症例は、高齢者の慢性疾患(高血圧・糖尿病・高脂血症など)、小児疾患、外傷である。見学してみて驚いたのは、外科的な処置が多いことであった。犬に噛まれたおばあさんや、ハブくらげに噛まれた観光客の男児や、転倒して怪我した人などがちょこちょこやってきた。先生は何度か傷口を縫ったり糸を抜いたりしていた。
 慢性疾患の患者さんに対しては、診察して、調子を聞いて、薬を処方、月に一度ほどは血液検査を実施していた。また、ちょうど、年に一度の竹富町実施の健康診断結果が出た時期で、慢性疾患で診療所にかかっていて健診を受けた方は健診結果を持って受診していて、先生が指導していた。見学したときには、保育園で風邪が流行しているということで、風邪をひいた幼児が何人も診察に訪れていた。
慢性疾患の患者さんに対しては、診察して、調子を聞いて、薬を処方、月に一度ほどは血液検査を実施していた。また、ちょうど、年に一度の竹富町実施の健康診断結果が出た時期で、慢性疾患で診療所にかかっていて健診を受けた方は健診結果を持って受診していて、先生が指導していた。見学したときには、保育園で風邪が流行しているということで、風邪をひいた幼児が何人も診察に訪れていた。
見学した中で、特に印象に残っている例を3つ紹介する。
3歳の男児で、地元の子である。転倒事故。レントゲンより、股関節の脱臼が見られ、大腿骨骨頭の骨折の疑いがあった。骨折の場合、骨頭が壊死し、人工骨頭が必要になる可能性もあり、重症化の危険がある。また、股関節の脱臼のみでも幼児の場合では全身麻酔が必要ということで、八重山病院への搬送となった。八重山病院へ連絡。ヘリか船での搬送だが、船での搬送になった。八重山病院への紹介状を作成し、石垣島の港に救急車を手配したあと、船の時間に合わせて西表上原港まで僻地患者輸送車で搬送する。上原港までは車で約30分。ここで患者を船の船長に引き継ぐ。西表から石垣まで船で約40分。石垣の港から救急車で約20分で八重山病院に到着する。西表西部診療所診察後、約2時間で八重山病院への搬送が終了した。
高熱のため来院していたが、薬(おそらくストレプトマイシン)が効いたため、レプトスピラ症と診断。レプトスピラ症はレプトスピラという病原体が原因で起こる。亜熱帯地方で見られ、沖縄でも離島のほうにだけ存在する。レプトスピラはネズミが媒介し、ネズミの排泄物で汚染された土壌や水を介して主に経皮的に感染する。ウイルス性感染に症状がよく似ている。この男性はおそらくカヌーツアーの際に干潟に入ったときに足の傷を介して感染したと思われる。
39度の高熱。乳児は生後4,5ヶ月までは母体免疫を保有しているために風邪にはかからない。その時期に高熱を発している場合は髄膜炎などの重症疾患が予想されるため、多くの場合、ヘリ搬送となる。5ヶ月以降の乳児だと、突発性発疹という、高熱を発するが、さほど心配はいらない病気にかかる。まれに熱性痙攣を起こすこともある。発疹が出てくるのは解熱後である。この男児の場合、生後4ヶ月なので突発性発疹の発症にはやや早すぎる。搬送するべきかどうか岡田先生は迷ったようだったが、男児の機嫌がとてもよく、笑顔だったため、解熱剤を処方し経過観察。翌日の午前中にもう一度診療所に連れてくるように指示した。
 岡田医師は、沖縄出身でもなければ、自治医科大卒でもなく、中部病院プライマリケアコース出身でもない。県外から希望して診療所へやってきた。医師になって12年目の37歳である。以前は岡山大学の消化器外科にいて、肝移植のスペシャリストを目指していた。医師になって10年が過ぎた頃、ふと違和感を覚えた。医師になって10年目は一つの折り返し地点だという。研修、研究、博士論文が一通り終わり、これから先自分が何をしていくのか、みんな何かしら考える時期である。大学病院で10年働いた後だと、専門か病院勤務か研究のどれかに進むのが一般的である。岡田先生はどれに対しても疑問・抵抗を感じた。診断が確定した患者を前に、ルーチンワークや手術を繰り返すことにやりがいを見出せなくなってきていた。また、大学病院には自分の代わりはいくらでもいるのではないか、とも感じたという。そこで魅力を感じたのが総合医だった。病気だけでなく人間全体を診なくてはならない。また僻地では自分しかいない。そこに惹かれた。そうして、僻地の診療所に勤務したいと考えるようになったが、孤立した状態ではやりたくなかった。システムがしっかり整っているところ、仲間がいて勉強しながらできるところ、そう考えて沖縄県の診療所を希望した。そして、西表西部診療所勤務となり、今年で2年目である。
岡田医師は、沖縄出身でもなければ、自治医科大卒でもなく、中部病院プライマリケアコース出身でもない。県外から希望して診療所へやってきた。医師になって12年目の37歳である。以前は岡山大学の消化器外科にいて、肝移植のスペシャリストを目指していた。医師になって10年が過ぎた頃、ふと違和感を覚えた。医師になって10年目は一つの折り返し地点だという。研修、研究、博士論文が一通り終わり、これから先自分が何をしていくのか、みんな何かしら考える時期である。大学病院で10年働いた後だと、専門か病院勤務か研究のどれかに進むのが一般的である。岡田先生はどれに対しても疑問・抵抗を感じた。診断が確定した患者を前に、ルーチンワークや手術を繰り返すことにやりがいを見出せなくなってきていた。また、大学病院には自分の代わりはいくらでもいるのではないか、とも感じたという。そこで魅力を感じたのが総合医だった。病気だけでなく人間全体を診なくてはならない。また僻地では自分しかいない。そこに惹かれた。そうして、僻地の診療所に勤務したいと考えるようになったが、孤立した状態ではやりたくなかった。システムがしっかり整っているところ、仲間がいて勉強しながらできるところ、そう考えて沖縄県の診療所を希望した。そして、西表西部診療所勤務となり、今年で2年目である。
 西表の古い地区には地区の行事が多い。年に14個の行事。月に1,2回はある。岡田先生はそれらの行事に一年間欠かさず参加されていた。診療所に勤務するだけでなく、地域に溶け込むことが大事だと先生は言った。ある住民の方が「信頼できない医師はいらない、地域に入ってくるような人がいい」とはっきり言っていたのも印象的だった。離島でさらに古い集落では、人間関係がすごく密である。地域に溶け込むことで仲間同士のような感覚も生まれ、医師と島民の信頼関係ができやすいのであろう。岡田医師は1年間の勤務と行事を終え、ようやく信頼関係ができたようだ。島の高齢者の方も素直に話をしてくれるようになったという。(右:伝統行事アンガマーで踊る岡田医師)
西表の古い地区には地区の行事が多い。年に14個の行事。月に1,2回はある。岡田先生はそれらの行事に一年間欠かさず参加されていた。診療所に勤務するだけでなく、地域に溶け込むことが大事だと先生は言った。ある住民の方が「信頼できない医師はいらない、地域に入ってくるような人がいい」とはっきり言っていたのも印象的だった。離島でさらに古い集落では、人間関係がすごく密である。地域に溶け込むことで仲間同士のような感覚も生まれ、医師と島民の信頼関係ができやすいのであろう。岡田医師は1年間の勤務と行事を終え、ようやく信頼関係ができたようだ。島の高齢者の方も素直に話をしてくれるようになったという。(右:伝統行事アンガマーで踊る岡田医師)
医師と島民の信頼関係とともに、離島医療では島民の意識も大事だという。急患ではないのに、時間外や休日に平気で受診する人がいる。前々から調子は悪かったのに、平日の時間内には受診せず、仕事が無いときに受診する人が増えているという。診療所には医師が1人しかいないので、すべて1人で負担しなくてはならない。医師にストレスがたまっていく一方である。そうすると、限界だ、長くはいられない、と医師が感じてしまい、診療所勤務が短期間しかもたない。医師の努力だけではどうしようもないこともある。だから、島民の意識、診療所にかかる島民のマナーも大事なのである。医師が住み着きやすい環境を島民が確保してやる必要があるのだ。本当に急いでいる場合以外は時間外診療は遠慮する、健康に対する意識を高め定期健診も積極的に受ける、といった努力をすることで、医師のストレスは大きく軽減されるのではないか。
先生が一年勤務してきたなかで、大学病院と診療所との差、ジレンマを感じたこともある。診療所では最後まで自分で診られない。ある程度の重症だと県立八重山病院に搬送しなくてはならない。観光客に「ここじゃできないのか」と馬鹿にされ、悔しい思いをしたこともあった。そんなときに八重山病院の院長から「人に頼れ、自分の限界を知れ、自分の限界を超えたら人に頼れ、離島医療のABCはAnother doctor, Beside doctor, Call doctorなんだよ。」と言われ、すっきりしたという。離島医療では医師が自分しかいないから、と自分で何でもやらなければならないという意識にかられる。しかし逆に、自分しかいないからこそ、自分の限界を超えたことはやってはいけない。なにかあったあとでは、離島では誰もフォローしてくれないのだ。自分でできないことはできない、と認めてしまうこと。簡単そうで、実はすごく難しいことである。しかし離島で適切な治療を早く行うには、すごく必要なことなのだ。
沖縄の離島医療を継続させていくためには2,3年という比較的短いスパンで医師を派遣していくことが必要なのだ、と中部病院の医師は話していた。この件に関して岡田先生に意見を伺うと、賛同する意見が返ってきた。本来ならばやる気のある医師が長い期間勤務するのが理想ではある。住民の方々も信頼する医師に長くいて欲しいと強く感じている。実際今年は医師が変わらないというと安心するという。しかし実際には一人の医師がずっと離島の診療所に勤務するのは、体力的にも精神的にもすごく難しい。そうするとやはり、短い期間でも充分に信頼できる医師が勤務することが大事になってきるのではないか。医師から住民に歩み寄り、信頼関係を早く作るようにする。住民からも医師に歩み寄り、医師が勤務しやすい環境を作るようにする。こういったお互いの努力が欠かせなくなるように思う。
岡田医師にこれから先のことについて伺った。ずっと西表島に勤務するのかと伺うと、Noという答えが返ってきた。あと数年いるかもしれないが、ずっといるつもりはないという。以前までいた大学病院にはもどれない。技術的なブランクもあるし、そう簡単に戻れるほど甘くもない。ではどうするのか。自分の地元である中国地方での僻地医療に携わることや、沖縄での体験を他の人に伝えていくことなどを考えてはいるが、具体的にはまだ何も決めてはいない。
診療所に勤務した医師は、老若男女問わず、すべての患者の様々な分野のプライマリを診る。その患者の病態があるレベルを超えてしまうと、診療所ではケアできないため病院へ紹介する。ある1つの分野の専門性を追求するわけではない。いわゆる、浅く、広く診るわけである。こういった医師は、総合医、もしくは家庭医と呼ばれる。この総合医は日本ではなじみが薄い。今日本での多くの医師がある分野の専門医である。この日本では、一度離島の診療所で総合医を経験すると、そのあとに進む場所がとても少なくなる。専門から離れた、現代の医療から離れた、とみなされ元の場所には戻れない。かといって総合医として働ける場所は僻地など限られてくる。総合医の立場が日本では確立されてもいないのだ。
「総合医も、総合医という専門医であると思う。」と岡田医師は言った。肝臓の病気なら何でも診れるという医師が専門医なら、どんな患者が来てもプライマリケアなら対応できるという医師も専門医なのではないか。患者側からしても、総合医のところに行けば、とりあえずどうにかなる、自分自身の家庭医を持つ、ということはすごく安心するであろう。これは僻地に限ったことではないと思う。総合医を専門医として確立すること、これは日本全体の医療にとっても、僻地の医療にとっても有益なことなのではないだろうか。総合医を確立すると、僻地勤務のあと進む場所があるだろうし、逆に総合医が僻地の医療に携わることが今よりもたやすくなり、僻地医療の担い手が増えると思う。
今回の診療所見学では、診察のアットホームな雰囲気から、重症患者の搬送の様子、地域の行事など、様々な場面を垣間見ることができ、大変貴重な体験をさせていただいた。離島の診療所がどういうものなのか、わたしたちなりに理解できたように思う。離島の診療所から、医療の原点も感じられた。
研修後、今回のメンバー3人がそれぞれで、「自分自身は離島の診療所に勤務できるか?」、ということを考えてみた。3人のうち2人の答えは「NO」であり、わたしの答えは「わからない」であった。3人とも、大喜びで行きたいとは言えないな、と感じている。なぜか。
島での生活への不安、孤独、地元の人々との関係など色々挙がった。そして、大きな問題として、将来の不安を感じた。離島に永遠に勤務しようとは思えなかった。そして、現在の状況のままでは、離島診療所勤務のその後が見えてこないのである。診療所勤務で身に付けた総合医としての技術を生かせる場が少ないこと、診療所勤務では現代の医療から離れたとみなされる傾向にあることなどからそう思える。このように思って、僻地の診療所勤務をためらう人は少なからずいるように思う。
今回の研修以前では、離島の診療所勤務をやりたいけどためらう、という人はやるべきではないと感じていた。しかし、研修を終えた今では、やりたいと思った人がすんなりやれるような、そんな離島診療所勤務の体制も必要なのではないか、と感じている。 (2章 文責:豊福)
 ありきたりな表現だが、珊瑚礁の海は青く澄んでいて、砂浜はうそのように白い。漂着物のほとんどは韓国や台湾からのものと思われ、ハングルのミネラルウォーター「泉の水」や漢字の「可口可楽」が所々に打ち上げられている。日本の西南端に位置するこの小島は、東京で夜のとばりが下りる頃に、やっと夕陽が色づき始めるような位置にある。 経度にしておよそ15度、実質的には東京と1時間の時差がある。
ありきたりな表現だが、珊瑚礁の海は青く澄んでいて、砂浜はうそのように白い。漂着物のほとんどは韓国や台湾からのものと思われ、ハングルのミネラルウォーター「泉の水」や漢字の「可口可楽」が所々に打ち上げられている。日本の西南端に位置するこの小島は、東京で夜のとばりが下りる頃に、やっと夕陽が色づき始めるような位置にある。 経度にしておよそ15度、実質的には東京と1時間の時差がある。
鳩間島は八重山諸島西表島の北約7kmに浮かぶ小さな島で、面積は1平方km強、周囲はおよそ4kmである。実際に鳩間島の一周道路道路を歩いてみたところ、ぐるりと一周するのに50分とかからなかった。人々が住む家屋は港がある島の南側に集中しており、それ以外のほとんどの部分は亜熱帯性の植物が生い茂る原野である。
島の人々の生活は、海と山とからの豊かな恵みを受け、今なお半ば自給的な色彩を少なからず残している。現金収入を得る手段としては民宿経営(島に5軒)や傭船、漁業、牧畜などが個人規模で行われているにすぎない。
竹富町が発表する人口動態表によると、2003年7月末現在の鳩間島の人口は57人(男性36人・女性21人)である。戦後は急激な過疎化に悩み、本土復帰後は診療所が閉鎖され、小中学校も廃校の危機に瀕した。島で最後の公の機関である小中学校をなんとしてでも存続させようとして(それが島の存続のための必要条件だと島民たちは考えていた)、鳩間島の人々は里親制度を利用し石垣島の孤児院から子どもたちを引き取って、鳩間小中学校に通わせるという独特の方法を取ってきた。現在では日本全国から不登校の子どもたちが鳩間小中学校に集まってきている。
これについては、森口豁氏の『子乞い』(凱風社)というルポルタージュが非常に詳しいので、興味の方は参照されたい。また『子乞い』を原作に据えて、尾瀬あきら氏がコミック化した『光の島 1〜6』も小学館から出ているので、同時に紹介する。
 西表島の西部診療所の医師は、月に一度鳩間島を訪れて巡回診療を行っている。毎月第二水曜日に行われることになっており、私たちは2003年8月13日水曜日に同行させて頂いた。西表島の港から岡田医師を乗せて出発した傭船は、およそ15分で鳩間島の港の桟橋に着く。岡田医師によれば、冬の間は海が荒れ風も冷たいので、意外に厳しい時間なのだという。
西表島の西部診療所の医師は、月に一度鳩間島を訪れて巡回診療を行っている。毎月第二水曜日に行われることになっており、私たちは2003年8月13日水曜日に同行させて頂いた。西表島の港から岡田医師を乗せて出発した傭船は、およそ15分で鳩間島の港の桟橋に着く。岡田医師によれば、冬の間は海が荒れ風も冷たいので、意外に厳しい時間なのだという。
西表島からの船がつく港からコミュニティーセンターという名の公民館まで、島では稀な舗装道路を歩いて3分ほどだ。巡回診療はこのコミュニティーセンターの一角で行われている。診察に使われる小部屋には旧式のクーラーがついているが、ほとんど涼しくならないので、医師も患者も汗だくになりながら診察が進められていく。しかしだれもが暑さには慣れていて、不平を言う者はいない。
今回の患者は、全部で6人。島の総人口の1割が訪れている計算になるが、患者はみな高齢の方だった。高齢者が多い鳩間島の人口構成を考えれば自然なことだろうし、比較的若く、体の自由がきく島の人々は、船で一時間の石垣島の医療施設まで足を伸ばすことが多いという事実も反映しているだろう。
 診療は次のように進められていく。患者がいすに座り、名前を述べる。一度かかったことがあれば、岡田医師の鞄の中からカルテがでてくるし、新規の患者であればその場で新たにカルテを作ることになる。「盆は忙しかった?」などと世間話をしながら、簡単に問診をし、胸の音をきき、いつも飲んでいる薬はまだあるかどうか確認する。もし、薬の残りが少なければ処方箋を書いて、翌日の郵便船で届くように手配する。これらを一通り終えると、岡田医師は次の患者を診察室に招き入れる。
診療は次のように進められていく。患者がいすに座り、名前を述べる。一度かかったことがあれば、岡田医師の鞄の中からカルテがでてくるし、新規の患者であればその場で新たにカルテを作ることになる。「盆は忙しかった?」などと世間話をしながら、簡単に問診をし、胸の音をきき、いつも飲んでいる薬はまだあるかどうか確認する。もし、薬の残りが少なければ処方箋を書いて、翌日の郵便船で届くように手配する。これらを一通り終えると、岡田医師は次の患者を診察室に招き入れる。
患者らが気にかけているのは、血圧が高いとか、糖尿が出るとか、中性脂肪の値が思わしくないなどという、身近で慢性的な症状が多かった。なかには、石垣島の医療施設から医薬品だけを届けてもらっているという患者もいたが、診察なしで薬だけもらうのはあまり良くないから巡回診療を積極的に利用するようにと、岡田医師がすすめる場面もあった。
6人の患者の診察が終わると、一人の若い女性がいすに腰掛けた。鳩間小中学校の養護教諭である。巡回診療の日程に合わせて、小中学校での講演を依頼したいとのことであった。テーマは生活習慣病で、子どもたちに酒やたばこの怖さについて教えてほしいとのことで、岡田医師はその場で快諾した。
『光の島』の紹介で触れたように、鳩間小中学校の児童・生徒は基本的に鳩間島以外の学校からの転校生である。様々な背景を持った子どもたちがこの島の学校で学んでいるわけだが、その生活指導には学校関係者や里親をなさっている島の人々も頭を痛めているらしい。一学期の終わりには、何人かの生徒が集団で飲酒・喫煙をしているところを見つけ、厳しく指導したばかりだという。
巡回診療は月に一度しかないが、大きなけがや、突然の発作がいつ起こるかはわからない。そうした緊急時には、海上保安庁のヘリコプターによって石垣島の県立八重山病院に患者を緊急搬送するシステムが確立しており、年に数回からの出動がある。
急患が発生した場合は、島で唯一の医療関係者である鳩間小中学校の養護教諭が、西表島西部診療所の岡田医師に電話で報告し、岡田医師が緊急搬送が必要であると判断した場合、海上保安庁にヘリの出動要請をすることになっている。こうした一見煩雑な手続きを取り決めているのには、実は理由がある。
数年前、鳩間島でインフルエンザが流行した際に、島の人々が直接ヘリを要請したことがあった。ところが搬送された患者の症状があまり重くなかったため、後になって緊急搬送の必要性があったのか否か議論になってしまった。緊急搬送に必要なマンパワーと経済的価値は小さくなく、不要なヘリ出動は最小限に抑えなくてはならない。それゆえに、事態の緊急性の判断を岡田医師に委ねるという現在の方法が取られるようになったのである。
 岡田医師が西表にいる際に「離島では予防医療が容易かつ有効だ。」とおっしゃっていた。人口がきわめて少ないことに加えて、食生活などの生活習慣が一様なことから、住民全員の健康状態を把握して、体調を維持するための的確な助言や指導を行うことが他に比べて容易なはずである。もちろん島民全員が巡回診療を活用しているわけではないし、生活習慣についての指導もまだ十全とまではゆかない様子ではあったが、今までは医師が単身で行っていた巡回診療の際に、今年度から西表島の保健師の同行を得られるようになったこともあり、医療側からの取り組みが今後も精力的に続けられてゆくだろう。(写真:鳩間島へ医師と保健師を運ぶ傭船)
岡田医師が西表にいる際に「離島では予防医療が容易かつ有効だ。」とおっしゃっていた。人口がきわめて少ないことに加えて、食生活などの生活習慣が一様なことから、住民全員の健康状態を把握して、体調を維持するための的確な助言や指導を行うことが他に比べて容易なはずである。もちろん島民全員が巡回診療を活用しているわけではないし、生活習慣についての指導もまだ十全とまではゆかない様子ではあったが、今までは医師が単身で行っていた巡回診療の際に、今年度から西表島の保健師の同行を得られるようになったこともあり、医療側からの取り組みが今後も精力的に続けられてゆくだろう。(写真:鳩間島へ医師と保健師を運ぶ傭船)
一方で、住民側からの歩み寄りも必要と感じられた。島の人々は無医島に住んでいるという危機感が意外なほど希薄で、ヘリポートがあるから、いざという時はそれにたよればよいのだという声がほうぼうから聞かれた。しかしながらそうした意識が住民のなかで広がることによって、島民は長い間医師の診察を受ける機会を持たず、本来なら未然に発見して予防できるはずの疾病までが重症化する状態に拍車をかけてしまっているおそれがある。もちろん30年来、日常的な医師の診察を受けることが不可能であるという現実に甘んじざるを得なかった鳩間島の人々が、仕方なくその現状に順応してきたことは責められるべきことではない。
ただ、住民の健康に対する意識の低さや緊急搬送についての無理解は、離島医療のコスト肥大化を招き、巡り巡って彼ら自身の島の存続にもマイナスの影響を与えかねないのではないかと危惧する。それを回避するために、巡回診療の機会が有効に活用されることを期待したい。
加えて、耳鼻科、眼科、精神科、心療内科などは、現在巡回診療が行われていないか、あるいは行われていてもその頻度がきわめて少ない診療科である。高齢者のなかには、目や耳を患う方も多いだろうし、特異な鳩間小中学校の存在を考えると、子どもたちの心のケアにあたれる専門家が島を訪れることには意味があると思われる。今後の診療科の拡大にも注目していきたい。
最後になったが、今回の研修でお世話になった中部病院の安次嶺院長、田仲医師、本村医師、豊川医師、そして岡田医師をはじめとする西表島西部診療所のみなさんに感謝の意を表したい。ありがとうございました。